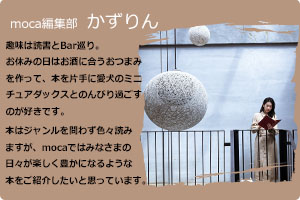むらさきのスカートの女
CULTURE
2023.03.25
👗ふとした日常の裏側にドラマが隠れているんです👗

何気ない日常の行動に狂気が含まれているとしたら
あなたも誰かに見張られているのかも……
著 者: 今村夏子
出版社:朝日文庫
定 価:682円(税込)
昨年(‘22年)6月30日に文庫化された本書を半年以上経ってから購入。
文庫の奥付は11月5日発行で第5刷でした。女性週刊誌の書評のキリヌキを古い手帳のポケットでみつけて思い出し、購入。
単行本は‘19年6月に刊行、翌7月には第161回の芥川賞を受賞しています。
月刊『文芸春秋』の芥川賞発表号で全文読んでしまったので、単行本は買いませんでした(版元さんゴメンナサイ)。
では、なぜ文庫本に注目したかというと、9本の芥川賞受賞についての著者のエッセイが文庫本化の特典としてついていたからです。エッセイを読むと、いわゆるフツーの主婦と同じ目線で、郊外の大型スーパーのフードコートで2歳のお嬢さんとご主人とで食事を楽しむ日常が、ほんわか描かれています。
そんな方が海外でも高く評価されている作品を生み出されているとは!
「ワタシにも……もしや」などと元気をもらえます(笑)。
とても面白くて高名な作品なので、失礼のないよう紹介をしなければ……では始めましょう。

【本書のあらすじ】
近所に住む「むらさきのスカートの女」と呼ばれる女性が気になって仕方のない〈わたし〉は、彼女と「ともだち」になるために、自分と同じ職場で働きだすように誘導し……(文庫本のカバーより)。とあるように、主人公の〈わたし〉と観察される「むらさきのスカートの女」の2人の女性を軸に物語は進みます(2人の名前は、次第に明かされていきます)。
冒頭から〈わたし〉は「むらさきのスカートの女」を、とことん仔細に観察します(滑稽なほど)。職を求めていることを知った〈わたし〉は無料の求人誌を使い、巧妙に自分の職場である高級ホテルの客室清掃の仕事に就かせます。
でも同じ職場にはなったものの〈わたし〉は「むらさきのスカートの女」との友情を得ることはできません。そのうち「むらさきのスカートの女」は職場で目立つ存在になっていき、〈わたし〉が引き起こした事件をきっかけに、意外なエンディングへと向かいます。表紙カバーのスカートから出ている2人分の脚が意味深ですね。
【作者について】
今村夏子(いまむらなつこ)氏は1980年、広島生まれ。2010年に『あたらしい娘』(その後、『こちらあみ子』に改題)で太宰治賞、翌年、三島由紀夫賞を受賞しています。‛17年には『星の子』が芥川賞候補にもなり、野間文芸新人賞を受賞。作品は少ないながら、常に賞に絡んでくる力量に脱帽!
でも、文庫本に収められているエッセイでは、生みの苦しみが吐露されています(芥川賞作家になったからには、変な作品は書けませんよね)。
芥川賞の受賞インタビューでは、「太宰治の『燈籠』が好きで、芥川作品はあまり知りません」と答えて記者からウケていました。

【舞台&背景】
最寄りの駅からはバスで30分ほどの、アーケードつきの商店街がある町に「むらさきのスカートの女」が暮らす木造2階建てのボロアパートがあります。近くには子供たちにからかわれる公園も。
「むらさきのスカートの女」を執拗に監視する〈わたし〉の住むアパートも同じ町内にあり〈わたし〉宛に裁判所から部屋の明け渡しの催告状が届いています。
そして物語が大きく動いていく「M&H」という高級ホテルは、その町からタクシーなら3千円、歩けば2時間ほどかかる距離にあり「むらさきのスカートの女」と〈わたし〉はバスに30分ほど乗り清掃の仕事に向かいます。
ホテルの客室清掃の仕事は著者が大学卒業後に転々としたアルバイトのうちのひとつで一番長く続いた仕事。
29歳の時に、シフトの都合で休みを言い渡されたときに、小説を書こうと突然思いついたと、文庫本の巻末エッセイに書かれています。客室清掃の経験が、創作の原動力になっているんですねぇ。
【レビュー&エピソード】
文庫本の帯には、17言語23か国・地域で翻訳出版されていて「世界も注目する才能」と称賛。
翻訳者の解説には「ほぼすべての描写に別の意味が隠されていることに気づかされた。この物語は一種のブラックコメディでありながら、言いようのない悲しみをたたえている」とあります。
ところで、逆の視点で平たく言ってしまうと“ストーカーにあやつられる可哀そうな女”の物語と言ってもいいのではないのでしょうか。「むらさきのスカートの女」はちゃんとした姓名があるのにあだ名をつけられ、からかわれています。
しかも、裕福とは言えなくとも、ささやかな幸せな暮らしをしていたのに〈わたし〉に目をつけられ、住み慣れた町を出ることになってしまう……。〈わたし〉の存在が恐ろしく感じられます。
さらに、この物語が恐ろしく感じるのは、登場する人物たちがすべて凡庸で、ヒーローもヒロインも不在なこと。生活や仕事シーンもすべからく「日常」(恋沙汰も含め)です。紹介されるエピソードも小さくつまらないものばかり(くだらなすぎて面白いのですが)。
それゆえに〈わたし〉の狂気がリアリティを持って迫ってきます。あなたやワタシの身近にも〈わたし〉がいるのかも。
お~怖……。