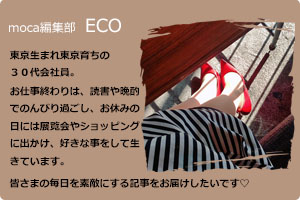日々のなぜ!?を解消!腹部膨満感の原因と対策をリサーチ♡
HEALTH
2025.09.02
皆さまこんにちは!moca編集部ECOです♡
「いつもよりお腹がぽっこりしている気がする」
「食後が苦しい」
「ガスが溜まっている感じがする」――
誰しも一度は経験したことがある“お腹の張り”。
体重が増えたわけでもないのにスカートがきつく感じたり、外出先で不快感が続いたりすると、とても気になりますよね😿💦
実はこの「お腹の張り(腹部膨満感)」は、消化器系のちょっとした乱れからホルモンバランス、生活習慣にいたるまで、さまざまな原因が関係しています。
今回はその代表的な原因と対策をリサーチしてみました✨

◆1.腸内にガスがたまる◆
食事や会話のときに空気を飲み込む「嚥下空気症」や、消化しにくい糖質が大腸で発酵することでガスが発生します。
特に豆類、玉ねぎ、ブロッコリーなどに含まれる「FODMAP」と呼ばれる発酵性糖質は、腸内細菌により分解されやすく、ガスを生じやすいことが知られています
(論文:Halmos EP et al., Gastroenterology, 2014)。
◆2.腸内環境の乱れ◆
便秘が続くと腸内に便やガスが滞り、張りや不快感を招きます💦
腸内フローラのバランスが乱れることも大きな要因。特に女性はホルモンの影響で腸のぜん動運動が弱まりやすく、便秘や膨満感を感じやすい傾向がありますので、要注意です!
◆3.ホルモンの影響◆
生理前に黄体ホルモン(プロゲステロン)が増加すると、水分を体にため込みやすくなり、むくみやお腹の張りにつながります。これは「月経前症候群(PMS)」の一症状としてもよく見られるものです。

◆4.過敏性腸症候群(IBS)◆
ストレスや自律神経の乱れが影響する「過敏性腸症候群」では、腹痛や下痢・便秘とともに膨満感を訴える方が多くいます。
研究によると、患者の70%以上が「腹部膨満感」を主要な症状として報告しているとされています。
(論文:Serra J. et al., Gut, 2001)。
~今日からできる5つの対策~
◆1.食事内容を見直す◆
ガスの発生源となるFODMAPを多く含む食品(玉ねぎ、豆類、小麦、乳製品など)を控えることで、膨満感が改善されるケースがあります。
「低FODMAP食療法」は科学的に有効性が確認されており、慢性的な膨満感に悩む方に推奨されることも・・・!
低FODMAP食療法については、また別記事でリサーチしてみようと思います😊🥗
◆2.ゆっくり食べて“空気”を飲み込まない◆
早食いや炭酸飲料の摂取は、空気を過剰に飲み込む原因になります。食事はよく噛んで、落ち着いて食べることが大切です🐻

◆3.腸内環境を整える◆
ヨーグルト、納豆、味噌などの発酵食品を取り入れるほか、食物繊維をバランスよく摂ることが推奨されます。
ただし、水溶性食物繊維(海藻類、オートミールなど)はガスを抑えつつ腸内環境を整えやすい一方、不溶性食物繊維(ゴボウ、豆類など)は摂りすぎると逆にガスを発生させやすいため、バランスがポイントです🌹
◆4.軽い運動で腸を動かす◆
ウォーキングやヨガなどの軽い運動は腸のぜん動運動を促し、ガスや便を排出しやすくします。
特に「ガス抜きのポーズ」と呼ばれるヨガ(仰向けで膝を胸に引き寄せるポーズ)は、実際にお腹の張りを和らげる効果が期待できますので、是非無理のないように気を付けながら試してみてください🌹
◆5.リラックスで自律神経を整える◆
ストレスは腸の働きに直結します。深呼吸、瞑想、アロマなどで副交感神経を優位にし、リラックスする時間を持つことで腸の動きが安定しやすくなります。
「マインドフルネス療法」が膨満感の改善に有効であると報告されています✨
(論文:Zernicke KA et al., Mindfulness, 2013)。
■さいごに・・・♡■
「お腹の張り」は単なる一時的な不快感にとどまらず、食生活や腸内環境、ホルモン、ストレスなどさまざまな要因が絡み合って起こる症状ということが分かりました😿💦
生活習慣の工夫を重ねることで、多くの方が「張り知らず」の快適なお腹を取り戻せます。もし膨満感が慢性的に続く場合は、疾患が隠れている可能性もあるため、医療機関への相談も忘れずに行ってくださいね🌹
自分の体のサインに耳を傾け、快適に過ごす工夫について、もっと情報を集めて皆さまにご紹介できたら良いなと思っております!
れではまた次回の記事でお会いいたしましょう~♡