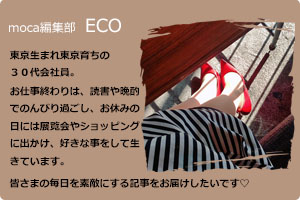大人の教養♡ワンランク上の会話も楽しめる~二十四節気を知る~
CULTURE
2025.04.05
皆さまこんにちは!moca編集部ECOです♡
日本には、春夏秋冬の「四季」があることは広く知られていますが、その四季をさらに細かく分けた「二十四節気(にじゅうしせっき)」という考え方があるのをご存じでしょうか?🌸
二十四節気は、太陽の動きに基づいて1年を24の節目に分けたもので、古くから農作業や暮らしの指標として使われてきました🐻!
時候の挨拶や普段の会話の中に、二十四節気を用いた粋な表現ができると、大人の魅力がぐっと増す気がしませんか?
今回の記事では、二十四節気についてリサーチをいたしました🐝🍓

◆二十四節気とは?◆
二十四節気は、中国で誕生した暦(こよみ)の考え方が日本に伝わったものです。
古代の人々は太陽の動きや自然の変化を観察し、それを季節の目安とすることで農作業の計画を立てていました。
日本では、気候や風土に合わせてこの24節気が取り入れられ、現在の暦にもその名残が見られます🍃
二十四節気は、春・夏・秋・冬の4つの季節をさらに6つに分けて、1年を24の節目(約15日ごと)に分けたもの。それぞれの節気には、自然や気候の特徴を表す美しい名前がつけられています✨
◆二十四節気の一覧と意味◆
🌸 春(2月〜4月)
・立春(りっしゅん)(2月4日頃)
春の始まり。暦の上ではこの日から春が始まります。
・雨水(うすい)(2月19日頃)
雪が雨に変わり、雪解けが始まる時期。
・啓蟄(けいちつ)(3月5日頃)
冬眠していた虫たちが土の中から目覚めるころ。
・春分(しゅんぶん)(3月20日頃)
昼と夜の長さがほぼ同じになる日。春の訪れを感じます。
・清明(せいめい)(4月4日頃)
すべてが清らかに生き生きとする時期。桜や花が咲き始めます。
・穀雨(こくう)(4月20日頃)
穀物を潤す恵みの雨が降る時期。

☀️ 夏(5月〜7月)
・立夏(りっか)(5月5日頃)
夏の始まり。新緑が美しくなるころ。
・小満(しょうまん)(5月21日頃)
すべての生命が満ちてくる時期。
・芒種(ぼうしゅ)(6月6日頃)
稲や麦などの苗を植える頃。
・夏至(げし)(6月21日頃)
一年で最も昼が長くなる日。
・小暑(しょうしょ)(7月7日頃)
本格的な暑さが始まるころ。
・大暑(たいしょ)(7月23日頃)
一年で最も暑さが厳しい時期。

🍁 秋(8月〜10月)
・立秋(りっしゅう)(8月7日頃)
暦の上では秋の始まり。
・処暑(しょしょ)(8月23日頃)
暑さが和らぎ始めるころ。
・白露(はくろ)(9月8日頃)
草花に朝露が降りるころ。
・秋分(しゅうぶん)(9月23日頃)
昼と夜の長さがほぼ同じになる日。
・寒露(かんろ)(10月8日頃)
朝晩が冷え込み、秋が深まるころ。
・霜降(そうこう)(10月23日頃)
朝に霜が降り始める時期。

❄️ 冬(11月〜1月)
・立冬(りっとう)(11月7日頃)
暦の上では冬の始まり。
・小雪(しょうせつ)(11月22日頃)
雪がちらつき始めるころ。
・大雪(たいせつ)(12月7日頃)
雪が積もり始める時期。
・冬至(とうじ)(12月22日頃)
一年で最も夜が長くなる日。
・小寒(しょうかん)(1月5日頃)
寒さが本格的に厳しくなるころ。
・大寒(だいかん)(1月20日頃)
一年で最も寒さが厳しい時期。

二十四節気は、自然と人間が調和して生きるための知恵が詰まっています。
現代社会では忙しい日々を過ごしている方も多いですが、二十四節気を意識することで、自然のリズムに沿った心穏やかな暮らしができるかもしれません💕
◆さいごに・・・♡◆
「啓蟄を過ぎて春の息吹を感じますね🌸😊」なんて粋な会話ができるようになりたいなと思いながら記事を書いておりましたが、皆さまは二十四節気を意識して生活をされたことはありますでしょうか?
季節の変わり目や、旬の食材、気候の変化などは身近に感じられますが、「言葉」で季節の移ろいや一年のサイクルを感じるのも、大人の教養として素敵ですよね✨
是非、日々の会話に取り入れて、より四季を深く感じてみていただけたら嬉しいです!
それではまた次回の記事でお会いいたしましょう~♡